top of page
ボディケア
腰痛


知ってる?柔軟性と可動性の違い!
皆さんは「柔軟性」と「可動性」の違いをご存知でしょうか? 似たような言葉ですが、実はそれぞれ意味が違います。この違いを知っておくと、より効果的に体を動かせるようになり、ケガの予防やパフォーマンス向上にもつながります。 柔軟性とは、筋肉や腱が「どれくらい伸びるか」を表すもの。たとえば前屈して手が床に届くのは、太ももの裏(ハムストリングス)などがよく伸びる=柔軟性が高いからです。こうした動きは、自分の力ではなく外からの力や重力などを使って行う「受動的な動き」です。いわゆる「体がやわらかい」というのは、この柔軟性のことを指します。 一方の可動性(モビリティ)は、「関節を自分の筋力でどこまで動かせるか」を示すものです。たとえば、寝転んだ状態で自力で脚を高く上げられるかどうかは、可動性の高さによります。これは「能動的な動き」であり、筋肉の柔らかさだけでなく、筋力、バランス感覚、神経の働きも影響します。 わかりやすく言うと、柔軟性は「どこまで伸ばせるか」、可動性は「どこまで動かせるか」。どちらか一方だけが高くても、思い通りに体を動かしたり、ケガを防ぐことは難

上村 拓矢
1月1日読了時間: 2分


足の「浮き指」って知っていますか?
浮き指とは、立っているときや歩いているときに 足の指が地面につかず浮いている状態 のことをいいます。 本来、足の指は地面をしっかりつかんで、体を支える大切な役割を果たしています。でも、浮き指になると、踏ん張る力が弱くなり、 転びやすくなったり、姿勢が悪くなったりする ことがあります。腰痛や肩こり、外反母趾の原因になることも。 原因はさまざまですが、「足に合わない靴」「歩き方のクセ」「運動不足」など、日常生活の中に潜んでいます。特にヒールや先の細い靴をよく履く人、子どもで運動の機会が少ない子にも多く見られます。 自分の足が浮き指かどうか気になる方は、 裸足で立ったときに足の指が床についているか をチェックしてみてください。指が浮いていたら要注意。 改善には、 足指を使うトレーニング (タオルを足の指でたぐり寄せる「タオルギャザー」など)や、 足に合った靴選び が効果的です。 足元から健康を見直して、元気に歩ける体を目指しましょう! #千葉県 #出張整体 #柏 #流山 #松戸 #姿勢 #整体 #ストレッチ #スポーツ #肩こり #腰痛 #疲労 #ブロ

上村 拓矢
2025年10月6日読了時間: 1分


実は腰に負担が大きい!?座り姿勢!
「立っているより座っているほうが楽」と感じる方は多いと思いますが、実は 座っているときの方が腰に大きな負担がかかっている ことをご存じでしょうか? 私たちの腰には「腰椎(ようつい)」という背骨の一部があり、座る姿勢ではこの腰椎にかかる圧力が増えやすいのです。特に、背中を丸めた“猫背”のような座り方は、腰への負担をさらに大きくします。ある研究では、立っているときと比べて、座っているときの椎間板(ついかんばん)にかかる圧力は約1.4倍、猫背の姿勢では約1.8倍にもなると報告されています。 なぜこうなるのでしょうか?座っているときは骨盤が後ろに傾きやすく、腰の自然なカーブが失われてしまいます。また、立っているときより腹筋や背筋のサポートが減り、腰にかかる負担が集中してしまうのです。 腰痛を防ぐには、椅子に深く腰掛け、骨盤を立てた姿勢を意識しましょう。背もたれやクッションを活用し、長時間同じ姿勢にならないよう、1時間に1回は立ち上がって体を動かすことも大切です。 「座っているから安心」と思わず、腰にやさしい座り方を日常から心がけてみてくださいね。 #千葉

上村 拓矢
2025年9月22日読了時間: 2分

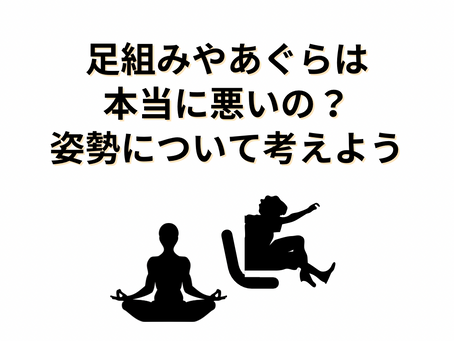
足組みやあぐらは本当に悪いの?姿勢について考えよう
「足を組むのは体に悪い」「あぐらは骨盤が歪む」などと、よく言われていると思います。確かに、これらの姿勢は長時間続けると体に負担がかかることがあります。でも、だからといって“絶対にやってはいけない”わけでもありません。 実は、どんな姿勢であっても「長時間同じ姿勢でいること」が、体にとって一番の負担になります。良いとされる姿勢でも、ずっと同じ状態でいると筋肉が疲れてきたり、血流が悪くなったりしてしまいます。 足を組んだり、あぐらをかいたりすることは、姿勢を一時的に変える手段としては自然なこと。これらの姿勢も快適にとれる場合もあります。大切なのは「無意識に長時間同じ姿勢を続けない」ことなんです。 たまに少し立ち上がって伸びをしたりすること。ストレッチや軽い運動を日常に取り入れるのも効果的です。 つまり、姿勢に“絶対の正解”はありません。体の感覚に耳を傾けて、無理なく動きを取り入れながら過ごすことが、結果的に体への負担を減らすポイントになります。

上村 拓矢
2025年9月21日読了時間: 1分


伸展型腰痛とは?関係する筋と注意すべき疾患
本日は腰部屈曲の動きとは逆の動き、伸展時の腰痛についてまとめてみました。 伸展型腰痛とは、腰を反らす(伸展する)動作で痛みが出るタイプの腰痛です。このタイプでは、 腹部の筋群(腹直筋・腹斜筋など)や、大腿直筋、大腿筋膜張筋(ももの筋肉) が関与していることがあります。 腹部の筋群の緊張が不十分だったり、大腿直筋や大腿筋膜張筋が過緊張していると、骨盤が前傾しやすくなり、腰椎に過剰な伸展ストレスがかかるため、腰痛を引き起こしやすくなります。 また、伸展で症状が悪化する代表的な疾患に腰椎 分離症 があります。脊柱管が狭くなることで神経が圧迫され、腰を反らすとさらに圧迫が強まり、 腰の痛みや下肢のしびれ、間欠性跛行 といった症状が誘発されます。立位や歩行で痛みが出て、前かがみになると楽になるという特徴があります。 伸展型腰痛の予防・改善にも、骨盤のアライメントを整え、関連筋の柔軟性や筋力バランスを保つことが重要です

上村 拓矢
2025年9月20日読了時間: 1分


腰痛のタイプ、あなたはどれ?運動方向でわかる4つの腰痛と関係する筋肉
腰痛と一口に言っても、原因やタイプはさまざまです。 腰痛には、体を「どの方向に動かすと痛いか」で分類する、 運動方向による分類 があります。今回はその中でも代表的な 4つのタイプ と、特に多い 屈曲型・伸展型腰痛に関係する筋肉 についてご紹介します。...

上村 拓矢
2025年9月18日読了時間: 2分


試合やレース前の入浴は要注意!?
「リフレッシュしたい」「スッキリした気分で臨みたい」と思って、試合やレースの直前にお風呂に入る方もいるかもしれません。でも、 その入浴、実はパフォーマンスにマイナスな影響を及ぼすこともあるんです 。 まず気をつけたいのが、 体力の消耗 。...

上村 拓矢
2025年9月15日読了時間: 2分


寒い日はウォーミングアップが“超”重要!
気温がぐっと下がる季節、体がなんとなく重く感じたり、動きづらくなったりしませんか?そんな寒い日こそ、「ウォーミングアップ(準備運動)」がとても重要なんです。 寒いと、私たちの筋肉や関節は冷えて硬くなりやすくなります。これは、筋肉の温度が下がることで、筋肉や腱の柔軟性が低下してしまうからです。簡単に言えば、冷えて硬くなったゴムは伸びにくいのと同じように、筋肉も冷えると伸びにくくなり、動きが鈍くなります。 さらに、寒さによって血流が悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が届きにくくなります。加えて、神経の伝達も鈍くなるため、体が思ったように動かず、反応が遅れることも。また、寒さから身を守ろうとして無意識に体が縮こまり、筋肉が緊張してしまうことも、柔軟性を低下させてしまったり、肩こりや腰痛の原因のひとつです。 このような状態でいきなり運動、スポーツをすると、筋肉や関節に無理な負担がかかり、ケガのリスクが高まります。だからこそ、寒い日の運動やストレッチ前には、 しっかりと体を温めることが大切 なのです。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予

上村 拓矢
2025年9月14日読了時間: 2分


ストレッチって本当に必要?
「ストレッチってやったほうがいいって聞くけど、どうなの?」 こんな疑問をお持ちの方、私なりの考えをまとめてましたのでぜひ、お読みください。 ストレッチには、ざっくり言うと以下のような効果があります。 筋肉の緊張をほぐす 血行を良くする 関節の動きをなめらかにする リラックス効果がある つまり、ストレッチは体を柔らかくするだけではなく、日々の疲れを取ったり、動きやすい体を保ったりするための“メンテナンス”のようなものです。 あなたが求めている変化は、ストレッチで叶うかも? でも、ここでちょっと考えてみてください。 「あなたが体に期待している変化」は、どんなものでしょうか? 肩こりや腰痛をなんとかしたい 疲れにくい体になりたい 姿勢を良くしたい 体を柔らかくしたい なんとなく、もっと元気に動けるようになりたい こうした悩みや希望、実は多くが ストレッチの効果の中に含まれている んです。 もちろん、ストレッチだけですべてが解決するわけではありませんが、「何か変えたい」と思っているなら、その第一歩としてストレッチはとても有効です。 続けることが、いちばん

上村 拓矢
2025年9月11日読了時間: 2分


角度や力加減が分からない!ストレッチの疑問
「ストレッチは体にいい」「ケガの予防になる」ってよく聞くとおもいます。でも、いざ自分でやってみると―― 「この角度で合ってるの?」 「どれくらい伸ばせばいいの?」 「痛いくらいの方が効くの?」 こんな疑問を感じたこと、ありませんか?実はこれ、とてもよくある悩みなんです。 正解は「痛気持ちいい」と感じる強さ ストレッチで大事なのは「無理なく、心地よく伸ばす」ことです。 力加減で言えば、10段階中の3〜5くらい。 伸びている感じはあるけど、「痛い!」とは感じない程度が理想です。 逆に、呼吸が止まってしまうほどの痛みはやめましょう。筋肉や関節を痛めてしまう危険があります。 正しい角度や姿勢って? ベースとなるフォームはありますが、実は「この角度が正解!」という決まりはなく、自分の柔軟性に合わせることが大切です。 無理に深く曲げるより、 正しい姿勢のまま、少しだけ伸ばす くらいでOK。 ポイントは、「伸ばしたい筋肉を意識できているかどうか」です。 その感覚があれば、少し伸びてるだけでも十分効果があります。 鏡で自分のフォームをチェックしたり、動画を見なが

上村 拓矢
2025年9月10日読了時間: 3分


“体が硬い=悪”ではない。ストレッチの必要性
「体が硬いんだけど、ストレッチって意味あるのかな?」 こう感じている人も多いと思います。 SNSで柔らかい人を見ると「自分には無理だな」と思ってしまうし、そもそも「やる意味あるの?」って疑問にもなりますよね。 そこでまず考えたいのは、「体が硬い=悪いこと」ではないということです。 私たちの体の柔らかさには個人差がありますし、「自分は硬い」と感じていても、日常生活に支障がないなら、無理に柔らかくする必要はありません。 たとえば、 歩く・座る・立つ動作で困っていない 特に体の不調もない こんな状態なら、ストレッチを絶対にしなきゃいけないわけではないんです。 でも反対に、 朝起きると腰がだるい 長く座っていると肩がつらい 年々、体が重く感じる こんなふうに「なんとなく不調」がある場合は、ストレッチが役に立つ可能性があるかもしれません。 柔軟性を高めることが「ゴール」ではなく、「体が楽になる」「動きやすくなる」ことが目的。 体が硬い人でも、ストレッチを少し続けることで、動きやすさや疲れにくさを感じることがあります。 たとえば、1日5分の簡単なストレッチで

上村 拓矢
2025年9月9日読了時間: 2分


冷湿布に「冷やす効果」はない!?
冷湿布=冷却ではない? 打撲や筋肉痛、捻挫などのときに使うことが多い「冷感湿布」。 スースーとした清涼感があり、「冷やしてくれるから効いてる感じがする」と思っていませんか? 実は、 冷湿布には「実際に冷やす効果」はほとんどない んです。 今回は、冷湿布の特徴や正しい使い方、冷却との違いについて分かりやすくまとめました! 冷湿布ってどんなもの? 冷湿布は、その名の通り「冷たく感じる」湿布です。 主にメントールやカンフルといった成分が含まれていて、皮膚に貼るとひんやりスースーした感覚を与えてくれます。 これは、 体の“冷感センサー”を刺激することで、脳が「冷たい」と錯覚 している状態。 つまり「冷たく感じるだけ」で、実際に皮膚の温度や炎症を直接冷やしているわけではありません。 どういうときに使うの? 冷湿布は、以下のような 急性の痛みや炎症 に使うと効果的です。 スポーツ後の筋肉痛 軽い打撲や捻挫 夏場の熱っぽいだるさ、など。 冷たく感じることで、 痛みを和らげたり、気持ちよく感じたり する効果があります。 本当に冷やしたいときはどうする? たとえば

上村 拓矢
2025年9月7日読了時間: 2分


疲労回復によるアイシングの目的
冷やすとどうして疲れが取れるの? 運動をすると、筋肉の中で「微細なダメージ」や「老廃物の蓄積」が起こります。 それが原因で翌日に筋肉痛やだるさを感じることがあります。 アイシングには以下のような働きがあるとされています: ・ 筋肉の温度を下げて、回復を促す → 冷やすことで筋肉の活動を落ち着かせます。 ・血流の変化で老廃物の排出をサポート → 冷やした後に血流が回復すると、たまった疲労物質が流れやすくなるとも言われています。 こうした作用が、 「翌日に疲れを残さない」体づくりに役立つ のです。 どんな時にやるといいの? アイシングが向いているのはこんな時: 長時間歩いた日や、立ち仕事の後 ・筋トレやランニングなどの運動後 ・夕方になると足がだるくなる人 ・疲労感が抜けにくい人 特に「足・ふくらはぎ・太もも」など、使った部位を冷やすのが効果的です。 ※注意事項として、沢山冷やせば効果が上がるということでもありません。10〜15分程度でも十分効果は得られます。 #アイシング #出張整体 #柏 #流山 #松戸 #姿勢 #整体 #ストレッチ #スポ

上村 拓矢
2025年9月4日読了時間: 1分


アイシングの3つの目的!怪我編
怪我直後のアイシングの3つの目的 ケガの直後にアイシングを行う理由は、大きく分けて3つあります。 1. 炎症を抑える 打撲や捻挫などをすると、体は自然と炎症反応を起こします。これはケガを治すための正常な反応なのです。それをアイシングをすることで血管が収縮し、炎症をある程度抑えることができます。 2. 痛みを軽減する 冷やすことで神経の働きが鈍くなり、痛みの感覚が一時的に和らぎます。これは、氷を当てた部分がジンジンして感覚が鈍くなるような感覚と同じです。痛みを早く抑えることで、不安やストレスも軽減できます。 3. 内出血や腫れを抑える ケガをすると血管が傷つき、内出血が起こります。これが腫れやあざの原因になります。アイシングで血流を一時的に抑えることで、内出血の広がりを抑えることができ、腫れも軽く済む場合があります。 ※冷やしすぎに注意! アイシングは便利な応急処置ですが、冷やしすぎると凍傷になってしまうリスクもありますので気をつけましょう。また、筋の慢性的な痛みには、温めるほうが効果的な場合もあるので、症状によっては医師や専門家に相談してください

上村 拓矢
2025年9月3日読了時間: 2分


アイシング!氷の重要性!
アイシングをするときは保冷剤よりも氷の方がおすすめです。 理由は大きく2つあります。 まず、氷は「熱を吸収する効率」がとても高いことです。氷が溶けるときには、周りの熱をたくさん奪います。この性質のおかげで、患部の熱を効率よく取り除き、炎症や腫れを抑える効果が期待できます。 一方、保冷剤は温度は低いですが、氷ほど熱を吸収する力は強くありません。 次に、安全性の面です。保冷剤はマイナス10度以下になるものもあり、直接肌に当てると凍傷になるリスクがあります。特に長時間使うと皮膚や組織が傷んでしまうこともあるので注意が必要です。 以上の理由から、外傷の応急処置では、氷を使ったアイシングがより効果的で安全です! #アイシング #出張整体 #柏 #流山 #松戸 #姿勢 #整体 #ストレッチ #スポーツ #肩こり #腰痛 #疲労 #ブログ #シェアお願いします

上村 拓矢
2025年9月2日読了時間: 1分


『ストレッチングの科学』から学んだ、ストレッチの正しい知識
先日、『ストレッチングの科学』(鈴木重行 著)という本を また 読みました。 (実は何度も読んでいます…汗) この本は、ストレッチに関する基礎知識から種類の違い、さらには生理学的・解剖学的な視点まで、非常に丁寧に解説されています。 たとえば、運動前に行う 動的ストレッチ...

上村 拓矢
2025年8月31日読了時間: 2分
bottom of page


