top of page
ボディケア
運動


角度や力加減が分からない!ストレッチの疑問
「ストレッチは体にいい」「ケガの予防になる」ってよく聞くとおもいます。でも、いざ自分でやってみると―― 「この角度で合ってるの?」 「どれくらい伸ばせばいいの?」 「痛いくらいの方が効くの?」 こんな疑問を感じたこと、ありませんか?実はこれ、とてもよくある悩みなんです。 正解は「痛気持ちいい」と感じる強さ ストレッチで大事なのは「無理なく、心地よく伸ばす」ことです。 力加減で言えば、10段階中の3〜5くらい。 伸びている感じはあるけど、「痛い!」とは感じない程度が理想です。 逆に、呼吸が止まってしまうほどの痛みはやめましょう。筋肉や関節を痛めてしまう危険があります。 正しい角度や姿勢って? ベースとなるフォームはありますが、実は「この角度が正解!」という決まりはなく、自分の柔軟性に合わせることが大切です。 無理に深く曲げるより、正しい姿勢のまま、少しだけ伸ばすくらいで大丈夫です。 ポイントは、「伸ばしたい筋肉を意識できているかどうか」です。 その感覚があれば、少し伸びてるだけでも十分効果があります。 鏡で自分のフォームをチェックしたり、動画を見な

上村 拓矢
2 時間前読了時間: 2分


“体が硬い=悪”ではない。ストレッチの必要性
「体が硬いんだけど、ストレッチって意味あるのかな?」 こう感じている人も多いと思います。 SNSで柔らかい人を見ると「自分には無理だな」と思ってしまうし、そもそも「やる意味あるの?」って疑問にもなりますよね。 そこでまず考えたいのは、「体が硬い=悪いこと」ではないということです。 私たちの体の柔らかさには個人差がありますし、「自分は硬い」と感じていても、日常生活に支障がないなら、無理に柔らかくする必要はありません。 たとえば、 歩く・座る・立つ動作で困っていない 特に体の不調もない こんな状態なら、ストレッチを絶対にしなきゃいけないわけではないんです。 でも反対に、 朝起きると腰がだるい 長く座っていると肩がつらい 年々、体が重く感じる こんなふうに「なんとなく不調」がある場合は、ストレッチが役に立つ可能性があるかもしれません。 柔軟性を高めることが「ゴール」ではなく、「体が楽になる」「動きやすくなる」ことが目的。 体が硬い人でも、ストレッチを少し続けることで、動きやすさや疲れにくさを感じることがあります。 たとえば、1日5分の簡単なストレッチで

上村 拓矢
1 日前読了時間: 2分


「アイシング」のベストな時間と間隔!
スポーツや日常生活でケガをしたとき、「とりあえず冷やしておこう」とアイシングをする方も多いと思います。でも、どれくらいの時間冷やすのが良いのか?どのくらいの間隔で繰り返せばいいのか?を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。 今回は、正しいアイシングの時間と間隔について、わかりやすくまとめてみました! ・1回のアイシング時間は「15〜20分」が目安 アイシングとは、氷や保冷剤を使って患部を冷やすことで、炎症や腫れ、痛みを抑える応急処置の一つです。 その際、1回あたりの冷却時間は15〜20分程度が適切とされています。 それ以上冷やし続けると、皮膚や筋肉が凍傷を起こすリスクがあるため注意が必要です。冷たさで感覚がなくなってきたら、それ以上続けず一旦中止しましょう。 ・アイシングの間隔は「1〜2時間おき」にすること なぜアイシングは1回で終わらず、「1〜2時間おき」に繰り返すのがよいのでしょうか? それには主に3つの理由があります。 ① 冷却効果が一時的だから 冷やすことで血管が収縮し、炎症や腫れを抑えることができますが、その効果は長くは続き

上村 拓矢
4 日前読了時間: 2分


可動性を高める〇〇ストレッチがヤバすぎる!
可動性(モビリティ)は、関節の動く範囲だけでなく、その動きをコントロールする能力を指します。単に筋肉を伸ばす柔軟性とは異なり、関節・筋肉・神経系が協調して機能することが重要です。そのため、可動性を高めるには動きの中で関節を動かし、神経筋の連携を促進するトレーニングが効果的です。 その方法の1つとして「ダイナミックストレッチ」があります。これは筋肉や腱を動的に伸ばしつつ、関節の可動域を徐々に拡大するアクティブなストレッチ方法です。 ダイナミックストレッチは単なるウォームアップ以上の意味を持ち、神経筋制御の改善に繋がるため、正しい動作パターンの形成やスポーツパフォーマンスの向上にも寄与します。静的ストレッチと違い、筋力低下を招くリスクも少なく、競技前の準備運動として理想的です。 ただし、可動域の限界を無理に超える動きや、急激な振り子運動は怪我のリスクを高めるため、コントロールされた範囲で丁寧に実施することが重要です。トレーナーとしては、個々の身体状況に合わせて動きの質を重視した指導が求められます。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我

上村 拓矢
1月3日読了時間: 2分


体が柔らかくてもコントロールできないと怪我をする!?
ストレッチをして体がよく伸びるようになるこれで怪我予防できたと思えますか?でも実は、柔軟性だけあっても怪我を予防することはできません。 柔軟性とは筋肉がどれだけ伸びるかという「受動的(受け身)な能力」。一方で大切なのは、その柔らかさを自分の力でコントロールできるかどうか=可動性(モビリティ)です。 たとえば、股関節が柔らかくても、スクワット中にその動きを支える筋力やバランス感覚がなければ、フォームが崩れて腰や膝に負担がかかります。これは「動けるけど支えられない」状態。逆に、自分の力でしっかり動かせる人は、柔軟性が多少低くても安全に動けます。 可動性があることで、動作を安定させ、体への負担を最小限に抑えることができます。つまり、柔軟性を高めたら、それを使いこなせる「可動性」もセットで鍛えることが、怪我をしにくい体づくりをしてると言えるでしょう。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア #千葉県 #柏 #整体 #スポーツ

上村 拓矢
1月2日読了時間: 1分


アスレティックトレーナーの役割とは?
アスレティックトレーナーの役割とはなんなのか?日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)のサイトを参照にご紹介していきます。 まず1つ目が、 スポーツ活動中の外傷・障害予防、 2つ目、 コンディショニングやリコンディショニング 、 3つ目、 安全と健康管理、 4つ目、 医療資格者へ引き継ぐまでの救急対応。 これら4つの役割に関する知識と実践する能力を活用し、 スポーツをする人の安全と安心を確保したうえで、パフォーマンスの回復や向上を支援する。 JSPO-ATは、学校部活動、クラブチーム、プロスポーツ、地域のスポーツイベント、医療機関、トレーニング施設など、さまざまな現場で活動しています。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア 参考リンク 日本スポーツ協会(JSPO)公式サイト https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid218.html #千葉県 #出張整体

上村 拓矢
2025年12月3日読了時間: 1分


筋・腱の柔軟性低下がもたらす痛み・障害への影響
私たちの身体は、筋肉や腱がスムーズに伸び縮みすることで、無理なく動くことができます。 しかし、トレーニングによる疲労、ウォームアップ不足、ケガや手術の後、さらには成長期の急激な骨の成長などによって、筋・腱はかたくなりやすくなります。こうした柔軟性の低下は、単に動きづらくなるだけでなく、思わぬ痛みやケガの原因になることがあります。 例えば、かたくなった筋や腱は付着部に負担をかけやすく、膝やかかとの痛みにつながることがあります。また、走ったり跳んだりする動きで筋肉がうまく伸びず、肉離れのリスクが高まることも。左右の柔軟性の差や、拮抗する筋肉のバランスが崩れると、姿勢や動きのクセにも影響し、知らないうちに体のどこかへ負担をかけてしまいます。 日ごろから軽めのストレッチやウォームアップを習慣にし、筋・腱を良い状態に保つことが、ケガの予防にもパフォーマンス向上にもつながります。自分の身体の「かたさ」に気づき、早めにケアしていきましょう。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市

上村 拓矢
2025年11月30日読了時間: 2分


脳の活性化!老化防止コーディネーショントレーニング
コーディネーショントレーニングは、「考えながら体を動かす」ことで脳に刺激を与える運動です。 手足をバラバラに動かしたり、リズムに合わせてステップを踏んだりする動きは、大脳や小脳を活発に働かせ、脳全体のネットワークを刺激します。そのため、日常生活で必要な注意力や判断力、段取りを組む力などの認知機能を高める効果が期待されています。 また、こうした運動は高齢者の脳の老化予防にも役立つとされています。ウォーキングのような単調な運動に比べ、「少し考える」刺激が加わることで、脳への負荷が適度に増え、認知機能の維持に良い影響を与えます。 特別な道具は必要なく、ボールを使ったキャッチや簡単なステップワーク、左右で違う動きをするエクササイズなど、身近な動きで始められるのも魅力です。 楽しみながら脳を活性化できるコーディネーショントレーニングをおこない、体を健康にしていきましょう。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア #千葉県 #出張

上村 拓矢
2025年11月29日読了時間: 2分


コーディネーショントレーニングとは?
コーディネーショントレーニングとは、簡単にいうと「体を思い通りに動かす力」を高めるための運動です。 走る・跳ぶといった体力そのものを鍛えるというより、 動きの質を良くする ことを目的としています。 たとえば、タイミングよく体を動かしたり、バランスを崩さずに姿勢を保ったり、急な動きの変化に対応したりと、日常生活にもスポーツにも役立つ能力が身につきます。 このトレーニングで鍛えられる能力は主に7つ。リズムに合わせて動く「リズム能力」、姿勢を安定させる「バランス能力」、状況に応じて動きを切り替える「変換能力」、合図に素早く反応する「反応能力」、体の各部分を連動させる「連結能力」、自分や物の位置をつかむ「定位能力」、力加減を調整する「識別能力」です。 子どもから大人まで幅広く効果があり、運動が苦手な人でも始めやすいのが魅力。転倒予防にもつながるため、健康づくりにもおすすめです。日常に簡単な動きを取り入れるだけでも、体が軽く動きやすくなりますよ。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください!

上村 拓矢
2025年11月28日読了時間: 2分


サーキットトレーニングとは?
サーキットトレーニングは、複数の運動を休憩をほとんど挟まずに連続して行うトレーニング方法で、短時間でも効率よく全身を鍛えられるのが特徴です。 スクワットやプランクなどの筋トレ、有酸素系の動きを組み合わせることで、 筋力・パワー・筋持久力・全身持久力といった多くの体力要因を同時に総合的に高められます。 種目と種目の間を長くしたり速くすると、全身持久力を高めるのに効果的です。 サーキットトレーニングで特に重要なのが「動作を正確に行うこと」です。急いでこなそうとするとフォームが崩れ、ケガの原因になったり、十分な効果が得られなかったりします。まずは正しい姿勢を意識し、無理のない範囲で丁寧に動くことが大切です。 種目や時間を調整すれば初心者から上級者まで取り組め、飽きにくく続けやすいトレーニング方法です。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア #千葉県 #出張整体 #柏 #流山 #松戸 #姿勢 #整体 #ストレッチ #スポーツ

上村 拓矢
2025年11月27日読了時間: 1分


スポーツ障害とは?
スポーツや運動を続けていると、多くの人が経験するのが「スポーツ障害」です。 これは、外力によるケガとは違い、長い期間にわたって同じ動作を繰り返すことで、筋肉や腱、靭帯、骨などに少しずつ負担が積み重なることで起こる障害です。 慢性的なスポーツ障害の特徴は、急に強い痛みや大きな腫れが出るわけではない点にあります。 熱っぽさや赤みなどの急性炎症反応はほとんど見られず、腫れも軽いことが多いため、見た目では気づきにくいのが厄介です。 しかし、運動すると痛みが続いたり、押すと痛い・力が入りにくいといった症状が現れ、放っておくと徐々に悪化していきます。 さらに、使いすぎによるダメージが蓄積しているため、治るまでに時間がかかることも特徴です。無理を続けると回復まで数週間〜数ヶ月かかることもあります。 「ちょっと痛いけど動けるから大丈夫」と放置しがちなスポーツ障害。 しかし早めに休養を取ったり、フォームの見直し、ストレッチや筋力バランスの改善を行うことで、悪化を防ぐことができます。 体が発するサインを無視せず、上手に付き合いながらスポーツを楽しみましょう。...

上村 拓矢
2025年11月26日読了時間: 2分

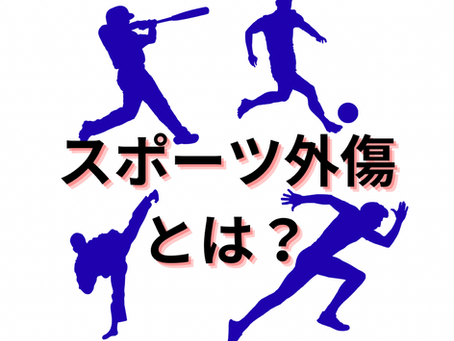
スポーツ外傷とは?
スポーツ外傷とは、 転倒・衝突・ひねり など、1回の大きな外力が加わった瞬間に起こるケガのことをいいます。 代表的なスポーツ外傷には、 捻挫(ねんざ) 、 打撲(だぼく) 、 骨折 、 脱臼 、 靭帯損傷 などがあります。たとえば、サッカーで足首をひねる、バスケットボールで相手とぶつかって転倒する、野球でボールが体に当たる、といった場面が典型的です。 スポーツ外傷が起きた直後は、無理に動かさず、まずは 患部を冷やす・安静にする などの応急処置が大切です。その後、腫れや痛みが強い場合は早めに医療機関を受診し、正しい評価と治療を受けることで、回復を早め再発予防にもつながります。 スポーツは楽しく健康的ですが、ケガのリスクもつきものです。正しい準備運動や体づくり、ルールを守ったプレーを心がけて、安全にスポーツを楽しみましょう。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア #千葉県 #出張整体 #柏 #流山 #松戸 #姿勢 #整体

上村 拓矢
2025年11月25日読了時間: 1分


スポーツ障害“ 間違った使い方” Mis useについて
スポーツを続けていると、「オーバーユース(使いすぎ)」という言葉を耳にすることがあります。しかし、実はもうひとつ見逃されがちな原因があります。それが 「ミスユース(Misuse)=身体の使い方の誤り」 です。ミスユースとは、運動のフォームや動き方が適切でないために、身体の特定部分に負担が集中し、痛みやケガにつながる状態のことを指します。 例えば、膝が内側に入ったままジャンプ着地を繰り返すと膝を痛めやすく、肩の力が抜けないまま投球すると、肩や肘への負担が増えます。また、ランニングで体幹がぶれていると、膝だけに衝撃が集まり「ランナー膝」を起こすこともあります。これらは決して「使いすぎ」ではなく、「使い方のクセ」が原因です。 ミスユースを防ぐには、まず自分の動きを知ることが大切です。動画を撮って確認したり、専門家にフォームチェックを受けたりすると改善の近道になります。 正しい身体の使い方を身につけることで、ケガを防ぐだけでなく、パフォーマンス向上にもつながります。運動を楽しむためにも、一度自分のフォームを見直してみましょう。 ※肩こり腰痛などの日常か

上村 拓矢
2025年11月24日読了時間: 2分


スポーツ障害“使わなすぎ”dis useについて
スポーツでケガをしたとき、多くの人は「安静にしていれば治る」と考えがちです。しかし、実はケガよりも厄介なのが“ディスユース(Disuse)”と呼ばれる現象です。ディスユースとは、 使わない期間が続くことで筋肉や関節の働きが弱ってしまうこと を指します。 例えば、足首をひねって動かさない期間が続くと、痛みは引いても筋肉が細くなったり、関節が固くなったりします。さらに、血流が悪くなったり、神経の反応が鈍くなることもあります。こうした変化はケガとは別の問題で、放っておくと「ケガは治ったのに動きが戻らない」「プレーするとまた痛める」といった悪循環につながってしまいます。 ディスユースを防ぐためには、 可能な範囲で早めに身体を動かすこと が大切です。患部を守りつつ、周囲の筋肉のトレーニングをしたり、ストレッチを行うだけでも効果があります。また、専門家の指導のもとで段階的にリハビリを進めることで、競技復帰がスムーズになります。 ケガの回復には休むだけでなく、“正しく動かすこと”が重要。ディスユースを理解し、賢く身体をケアしていきましょう。...

上村 拓矢
2025年11月23日読了時間: 2分


スポーツ障害“使いすぎ”over useについて
スポーツをしていると、「なんとなく痛い」「違和感が続く」と感じることはありませんか?その原因のひとつが、同じ動作を繰り返しすぎて起こる オーバーユース(使いすぎ) です。 走ったり跳んだり、腕を振ったりといった動作を続けることで、筋肉や骨、腱に少しずつ負担が蓄積し、やがて痛みとしてあらわれます。 代表的なオーバーユースの障害には、走りすぎで起きる疲労骨折やシンスプリント、膝の前が痛くなるジャンパー膝、肘に負担がかかるテニス肘などがあります。どれも最初は軽い痛みでも、無理を続けると長引いたり、競技を休まなければならなくなったりすることもあります。 予防のポイントは、 練習量と休息のバランスをとること 。さらに、ストレッチや筋トレで体を整え、正しいフォームを身につけることも大切です。 痛みを感じたら「これくらい大丈夫」と我慢せず、早めに対処することで重症化を防げます。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア #千葉県 #

上村 拓矢
2025年11月22日読了時間: 2分


スポーツ障害の「3つの“use”」とは?
スポーツ障害や日常の運動で起こるケガの背景には、「3つの“use”」と呼ばれる考え方があります。 まず オーバーユース(Overuse) 。これはその名の通り「使い過ぎ」が原因です。同じ動きを繰り返したり、負荷をかけ続けたりすることで、筋肉や関節に負担が蓄積し、痛みが出やすくなります。 次に ディスユース(Disuse) 。こちらは「使わなさすぎ」によるものです。運動量が減ったり、動く機会が少なかったりすると、筋力や柔軟性が落ち、ちょっとした動きでもケガにつながりやすくなります。 最後に ミスユース(Misuse) 。これは「間違った使い方」が原因です。姿勢やフォームが適切でない状態で体を動かし続けることで、特定の部位に負担が偏り、痛みや不調が起こりやすくなります。 この3つの“use”を知るだけでも、日々の体の使い方を見直すきっかけになります。無理なく、正しく、バランスよく体を動かすことが、スポーツ障害の予防につながります。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏

上村 拓矢
2025年11月21日読了時間: 2分


ランニングで起こる貧血の仕組みと予防法
ランニング愛好者の間で、あまり知られていない体の変化に 「フットストライク溶血」(foot strike hemolysis) があります。これは走るときに足が地面へ繰り返しぶつかる衝撃によって、血液中の赤血球が壊れてしまう現象です。 赤血球は全身に酸素を運ぶ大切な細胞ですが、足裏の細い血管を通る際に強い圧力がかかると、まれに壊れやすくなります。 「溶血」と聞くと怖い印象があるかもしれませんが、フットストライク溶血は 多くの場合とても軽度 で、症状が出ないことも一般的です。普段通り走れているなら、特に心配はいりません。ただし、長距離ランナーでは、血液検査で赤血球がやや減ったり、鉄不足が進みやすくなったりすることがあります。 予防としては、 クッション性のあるシューズを選ぶこと 、 硬い路面を避けること が効果的です。また、急に走る距離を増やさず、体の疲れと相談しながらトレーニングすることも大切です。 走ることは健康にとてもよい習慣ですが、自分の体がどんな反応をするか知っておくと安心です。気になる疲れや貧血症状がある場合は、早めに医療機関に相

上村 拓矢
2025年11月20日読了時間: 2分


競技者に多い鉄欠乏性貧血とは?
競技に取り組む人に特に多いのが「鉄欠乏性貧血」。これは、体に必要な鉄が不足することで、酸素を運ぶ赤血球がうまく作れなくなる状態です。 鉄が足りないと、息が上がりやすくなったり、疲れやすくなったり、「最近パフォーマンスが落ちた気がする…」という変化が表れます。 競技者は汗で鉄が失われやすく、筋肉量が増えることで鉄の必要量もアップします。さらに、長距離系の競技では、走る衝撃などによる微小な出血が起こることもあり、一般の人より鉄不足になりやすいのです。 予防には食事が重要です。赤身の肉や魚、レバー、ひじき、ほうれん草など鉄を多く含む食品をしっかりとることが大切。ビタミンCと一緒に食べると吸収率が上がります。また、疲れやすさが続くときは早めに検査を受けることも大事です。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア #千葉県 #出張整体 #柏 #流山 #松戸 #姿勢 #整体 #ストレッチ #スポーツ #肩こり #腰痛 #疲労 #ブロ

上村 拓矢
2025年11月19日読了時間: 1分


スムーズなスポーツパフォーマンス!「運動連鎖」とは
スポーツの動きを上手くするために大切なポイントに、「運動連鎖」というものがあります。 運動連鎖とは、 体の各部位の動きがつながり、力やスピードが全身へスムーズに伝わること を指します。 例えば、野球の投球では、足で踏み込む力が体幹へ、そして肩や腕、最後に指先へと流れるようにつながっていきます。この流れがスムーズなほど、無駄なく強いボールを投げられるのです。 逆に、どこか一つの動きだけを良くしても、他の部分の動きが乱れていると十分に力を発揮できません。たとえば、肩の可動域を広げても、体幹が安定していなければ腕の動きは活かせません。これは、全身が一つのチームとして連携していないからです。 スポーツのパフォーマンスを高めるには、体全体が協調して動くことが欠かせません。部分的なトレーニングも大事ですが、 全身のつながりを意識した動きの改善 こそが上達への近道です。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くしたい方はぜひお越しください! 千葉県柏市柏駅から徒歩4分 アスレティックルームボディケア #千葉県 #出張整体

上村 拓矢
2025年11月18日読了時間: 2分


パフォーマンスを上げる!心と体のベストな状態
スポーツで最高の力を発揮するためには、体の準備だけでなく「心の状態」を整えることが欠かせません。そこで重要になるのが、 興奮(覚醒)の最適水準 という考え方です。 これは「ちょうどよい緊張感」のことで、リラックスしすぎても集中できず、逆に緊張しすぎても体が硬くなってしまい、本来のパフォーマンスが発揮できないというものです。 この関係は「逆U字モデル」としても説明され、興奮が低いとぼんやりして動きが鈍くなり、高すぎると判断力が落ちてミスが増えるとされています。つまり、その中間にある“最適な覚醒レベル”に入ることが、スポーツではとても重要です。 その状態をつくるためには、深呼吸や音楽、試合前のルーティン、ウォーミングアップの強度調整など、自分に合った方法を探していくことがポイントです。心と体のスイッチがちょうどよく入ったとき、動きのキレや集中力が高まり、パフォーマンスが自然と引き出されます。 自分にとっての「最適な緊張感」を知ることが、スポーツの大きな武器になるのです。 ※肩こり腰痛などの日常からの体の不調、スポーツで怪我予防や動けるように体を軽くし

上村 拓矢
2025年11月17日読了時間: 2分
bottom of page
